【企業担当者向け】地政学リスクのおすすめ書籍8選!入門・面白い・社会人としての必読本まで
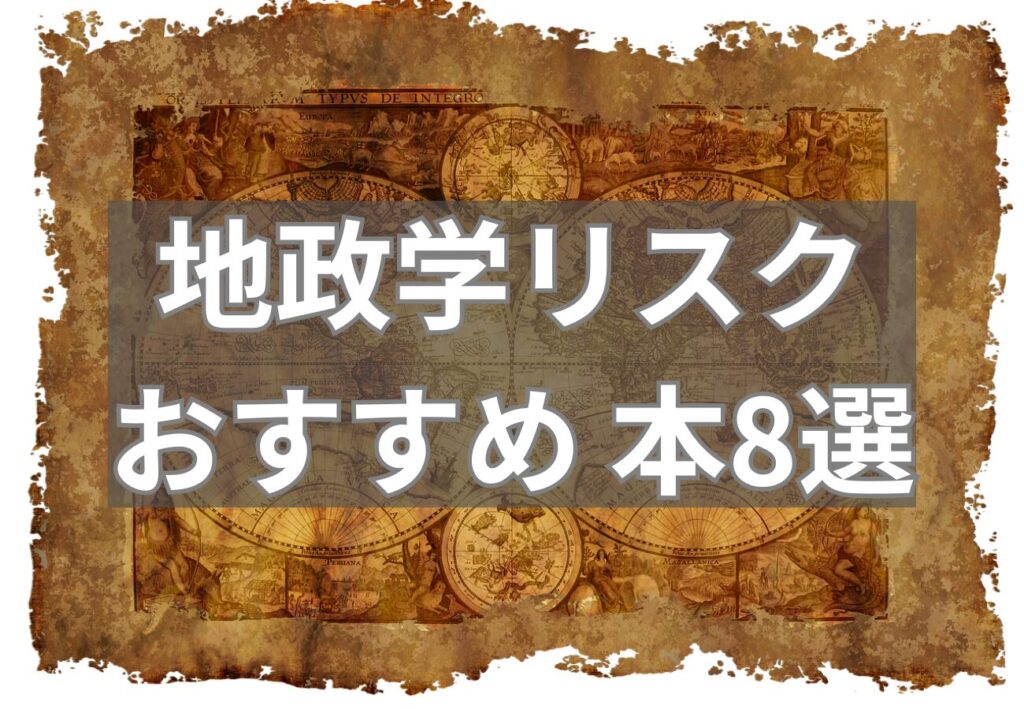
地政学リスクは、サプライチェーンの寸断や規制強化、市場の急変動など、ビジネスの現場に直結する課題につながることから、現代の経営者に必須のテーマとなっています。
この記事では、地政学リスクを体系的に理解できるおすすめの本を紹介します。
地政学リスクの概要についてもわかりやすく解説しますので、基本的な情報を抑えたうえで自分にあった本の選定にお役立ていただけます。
※本ページは広告・PRが含まれます
1. 地政学リスクを理解するためのおすすめ本
(1)地政学リスク:歴史をつくり相場と経済を攪乱する震源の正体
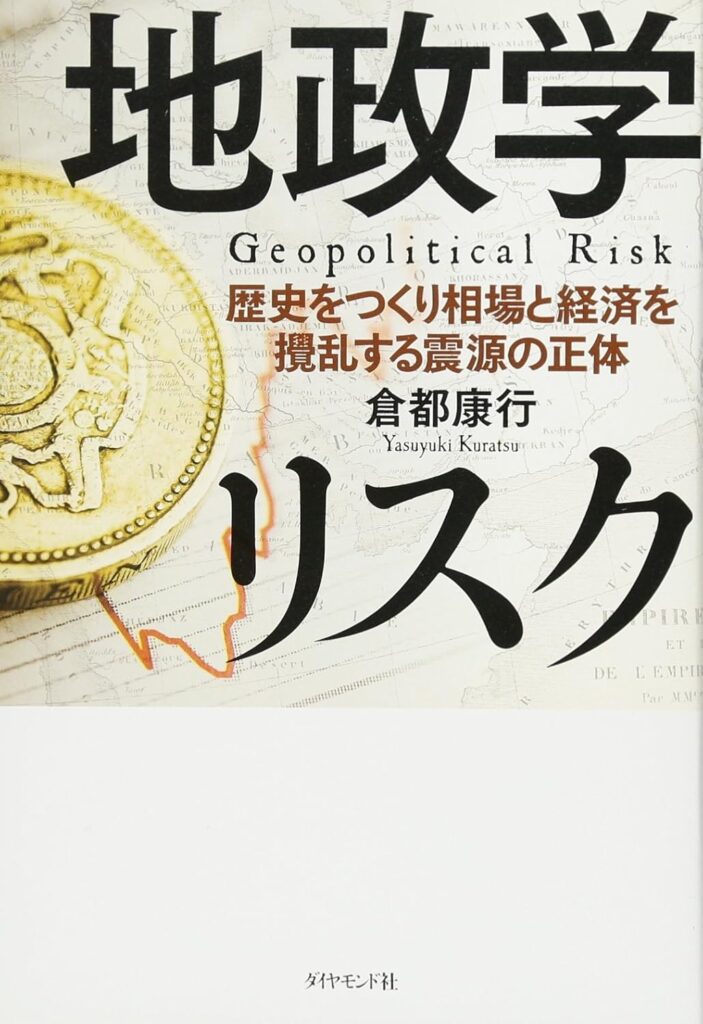
『地政学リスク:歴史をつくり相場と経済を攪乱する震源の正体』は、地政学がただの国際政治の理論にとどまらず、金融市場や経済活動にどのように直結するのかを明らかにする一冊です。
著者は為替や証券の現場経験を背景に、宗教対立や民族意識、イデオロギー、民主化運動、環境問題といった要因を体系立てて「リスク」として整理しています。
ワーテルローの戦いにおける情報戦から、同時多発テロ後の米国金融政策まで、歴史的な事例を引き合いに出しながら、地政学が経済のダイナミズムをどう揺さぶってきたのかが具体的に描かれています。日々の国際ニュースと金融市場の動きが一本の線でつながり、企業経営や投資判断においても欠かせない「外部環境の読み解き方」が見えてくる構成です。
こんな人におすすめ
- ・地政学リスクが経済と企業にどのような影響を及ぼすのか知りたい
- ・歴史的出来事をベースに地政学を理解したい
- ・金融系に権威性のある著者から学びたい
>>Amazonで『地政学リスク:歴史をつくり相場と経済を攪乱する震源の正体』を確認する
(2)あの国の本当の思惑を見抜く 地政学
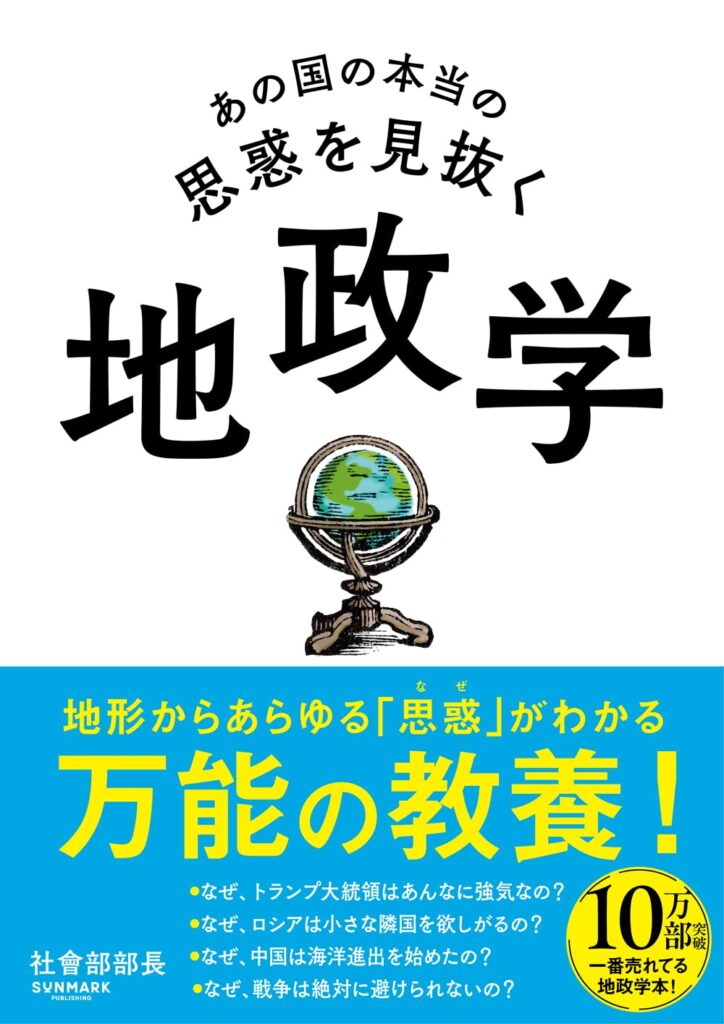
『あの国の本当の思惑を見抜く 地政学』は、各国の行動を「海洋国家」と「大陸国家」というシンプルな枠組みで捉え、ロシアの領土拡張やアメリカの世界戦略といった動きを論理的に理解できるよう構成されています。
最新ニュースを追うだけでは見えにくい背景を、長期的に変わらない地理的・歴史的要因から解説しているため、国際情勢を俯瞰する視座を自然に身につけられるのが大きな特徴です。
こんな人におすすめ
- ・ニュース報道の背景を理解したい
- ・各国の行動原理をシンプルに把握したい
- ・国際情勢を長期的な視点で捉えたい
>>Amazonで『あの国の本当の思惑を見抜く 地政学』を確認する
(3)現代日本の地政学:13のリスクシナリオ
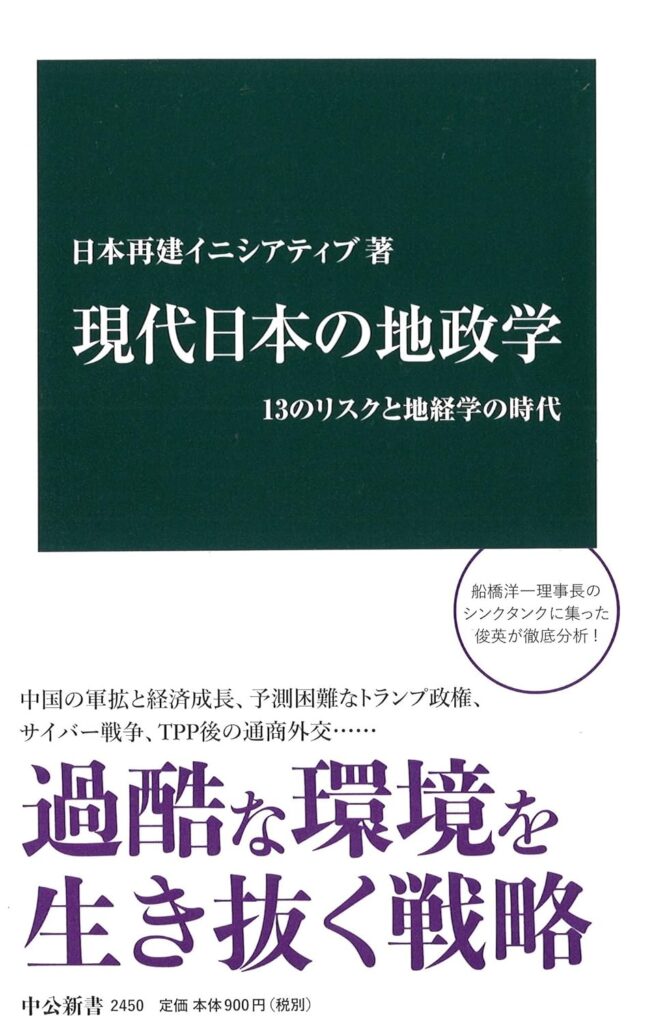
『現代日本の地政学:13のリスクシナリオ』は、日本を取り巻く国際環境を多角的に捉え、13の具体的なリスク事例に落とし込んで解説する一冊です。
領土問題や周辺国との緊張関係、エネルギーや経済安全保障といった日本固有の課題を切り口に、リスクがどのように顕在化し得るのかをシナリオ形式で提示しています。アメリカ、中国、ロシア、北朝鮮など日本に直接影響を及ぼす国々との関係を整理することで、企業が将来の不確実性を見据えた戦略を構築する手がかりを与えてくれます。机上の理論の紹介にとどまらず、現実的なリスクを可視化する構成となっている点が特徴で、日本企業が直面し得る課題を体系的に理解する上で、実務担当者や経営企画部門にとって有用な羅針盤となるでしょう。
こんな人におすすめ
- ・日本固有の地政学リスクを体系的に理解したい
- ・近隣諸国との関係や安全保障課題を戦略に反映させたい
- ・不確実性を踏まえたシナリオプランニングを学びたい
>>Amazonで『現代日本の地政学:13のリスクシナリオ』を確認する
(4)13歳からの地政学: カイゾクとの地球儀航海
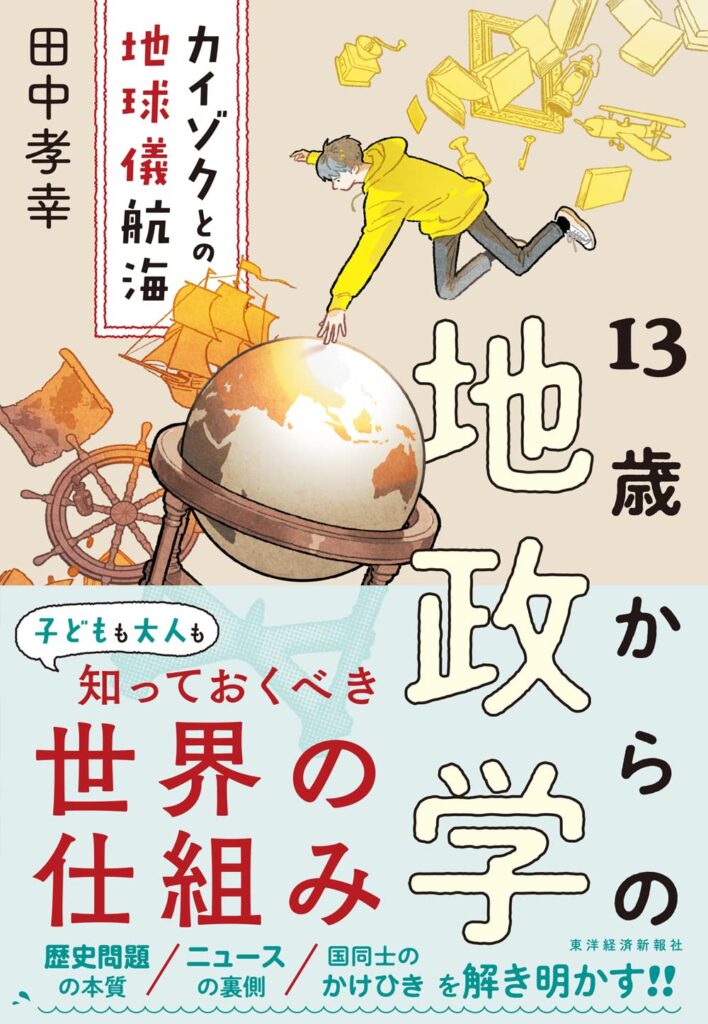
『13歳からの地政学: カイゾクとの地球儀航海』は、冒険物語を通じて地政学の基礎を学べる入門書です。海賊とともに地球儀を片手に航海するというユニークな設定のもと、海流や風、資源の偏在といった地理的要素が歴史的事件や国家間の対立にどのように影響してきたのかが自然に理解できるよう構成されています。専門用語をできるだけ避け、対話形式で展開されるため、大人はもちろん中高生にも「国際政治が動く仕組み」を直感的に掴むきっかけになる一冊です。史実の一部には解釈の違いもありますが、世界の見方を広げ、ニュースや国際情勢を捉える前提知識を得るには十分な内容を備えています。
こんな人におすすめ
- ・地政学の基礎を楽しく直感的に学びたい
- ・ニュースや国際情勢を理解する前提知識を身につけたい
- ・家族や子どもと一緒に学べる教材を探している
>>Amazonで『13歳からの地政学: カイゾクとの地球儀航海』を確認する
(5)ビジネス教養 地政学 (サクッとわかるビジネス教養)

『ビジネス教養 地政学(サクッとわかるビジネス教養)』は、国際情勢をビジネスパーソンの視点から効率的に理解できるよう設計された入門書です。アメリカの覇権戦略、中国やロシアの地理的制約、そしてホルムズ海峡などのチョークポイントといった具体的な事例を挙げながら、国家の行動原理を「ランドパワー」と「シーパワー」の対立といった基本概念で整理しています。豊富な図解や要点をまとめたサマリーが随所に盛り込まれており、短時間で全体像を掴める点も大きな特徴です。最新の国際情勢に応用できる視点も得られるため、深い専門知識がない人でも直感的に理解しやすい内容になっています。
こんな人におすすめ
- ・ビジネスの意思決定に直結する国際情勢の基礎を短時間で掴みたい
- ・図解や要点整理で効率よく地政学を理解したいビジネスパーソン
- ・最新の国際ニュースを戦略的な視点で読み解く力を養いたい
>>Amazonで『ビジネス教養 地政学 (サクッとわかるビジネス教養)』を確認する
(6)教養としての「地政学」入門
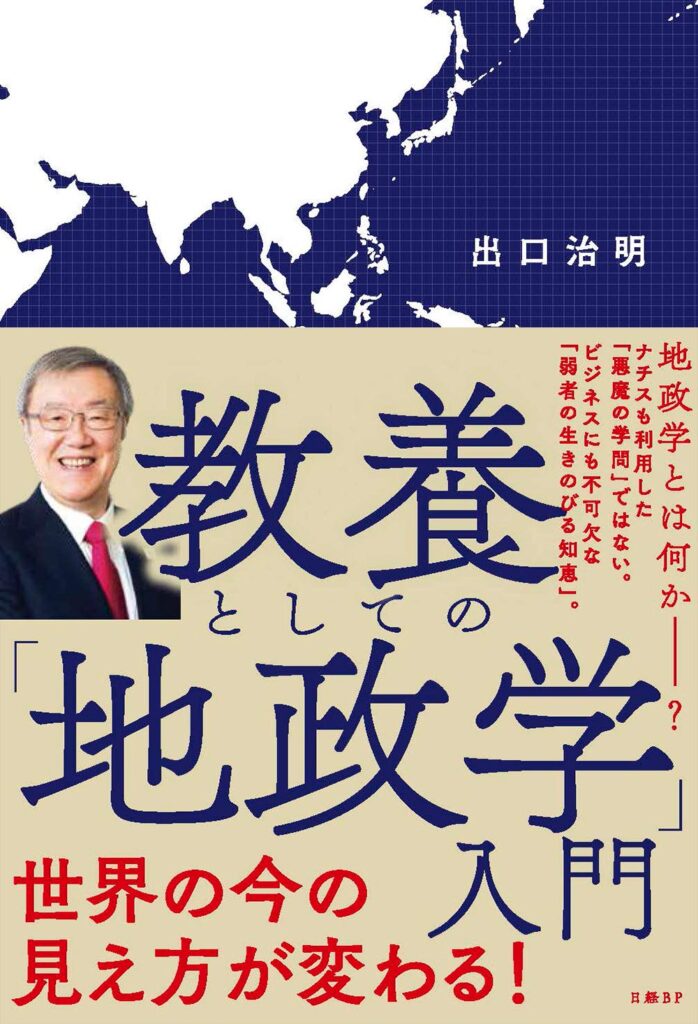
『教養としての「地政学」入門』は、古典的な地理決定論から現代のサイバー空間や宇宙に至るまで、地政学の射程を幅広く整理した入門書です。ヨーロッパの複雑な勢力均衡やローマ帝国の海洋支配、アメリカが築き上げた海洋覇権、そして日本列島が持つ戦略的な位置づけまで、多角的に解説されています。陸と海という視点から各国の歴史的行動原理を紐解くことで、なぜ国家が特定の政策を選択し、いかに資源や同盟を巡って動くのかが理解できる構成となっています。特に、日本が周辺国すべてと火種を抱えるという現実や、アメリカとの同盟関係が持つ意味を俯瞰的に捉えられる点は、現代のビジネス環境を考える上でも示唆に富みます。
こんな人におすすめ
- ・地政学を歴史から現代まで体系的に学びたい初心者やビジネスパーソン
- ・日本の戦略的位置づけや米国との同盟関係を多角的に理解したい
- ・サイバー空間や宇宙など新しい領域まで視野を広げたい
(7)90枚のイラストで 世界がわかる はじめての地政学
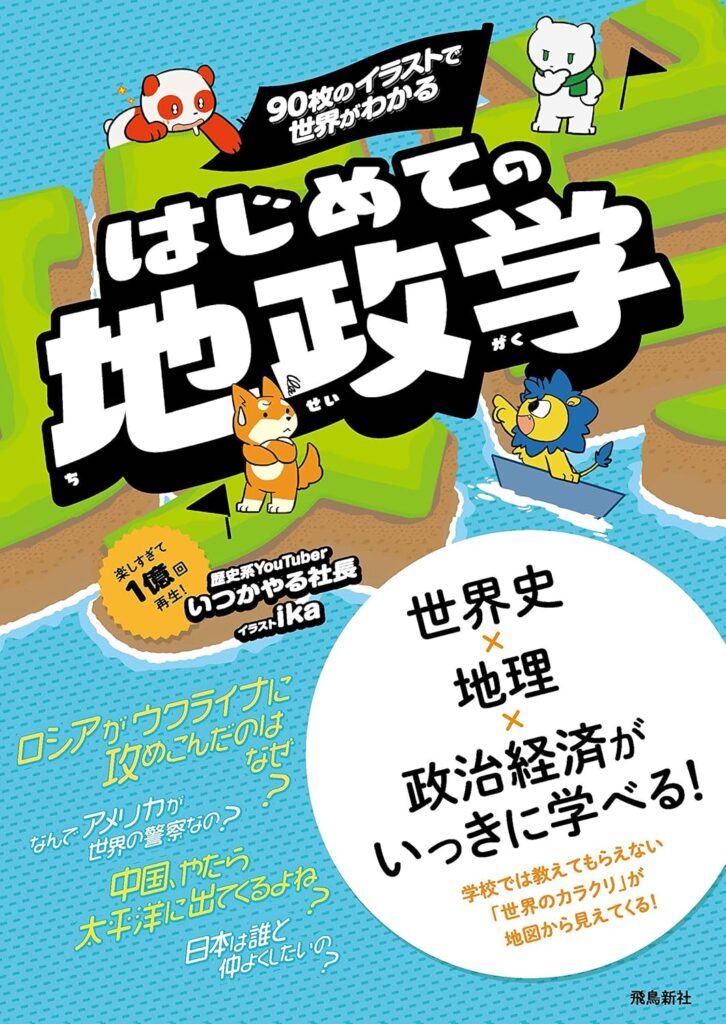
『90枚のイラストで 世界がわかる はじめての地政学』は、地政学の基本を豊富な図解で解説した入門書です。地形や気候、資源といった地理的条件が、国家の成り立ちや国際関係にどのように影響してきたのかを、古代文明から現代の国際情勢まで一貫して説明しています。文字だけでは理解が難しいテーマをイラストで補うことで、視覚的に直感的な理解が可能になっており、学習のハードルを下げてくれる点が大きな魅力です。内容は小中学生向けに工夫されていますが、大人にとっても基礎を学び直す格好の一冊となっており、国際ニュースや歴史の背景を理解するための足がかりになります。
こんな人におすすめ
- ・図解やイラストで地政学を直感的に理解したい
- ・子どもから大人まで基礎をやさしく学び直したい
- ・国際ニュースや歴史の背景をわかりやすく掴みたい
>>Amazonで『90枚のイラストで 世界がわかる はじめての地政学』を確認する
(8)地政学 ー地理と戦略ー
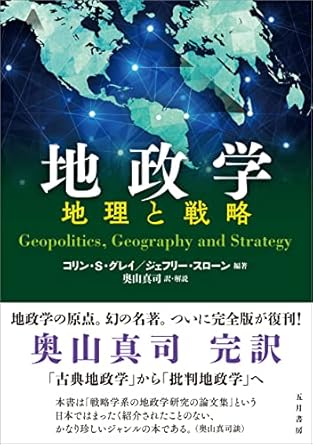
『地政学 ―地理と戦略―』は、地政学の古典理論を現代的な課題と結びつけて整理した本格的な一冊です。マッキンダーによるハートランド理論やランドパワーとシーパワーの対立構造といった伝統的概念を軸に、現代の海洋戦略、資源を巡る競争、気候変動、さらにはサイバー空間や宇宙といった新しい領域まで射程を広げています。国家が地理的制約の中でどのように戦略を構築し、国際社会での競争や協力を進めてきたのかを歴史的事例とともに解説しており、過去の理論が現代にも応用可能であることを示しています。加えて、地理や技術の変化が戦略環境をどのように再定義してきたかを考察する内容は、グローバルな視点で意思決定を行う企業担当者にとっても有用です。
こんな人におすすめ
- ・マッキンダーのハートランド理論など古典的概念を現代にどう応用できるか知りたい
- ・サイバー空間や宇宙といった新領域まで含めた地政学の射程を理解したい
- ・歴史的理論と最新の国際情勢をつなげて実務に活かしたいビジネスパーソン
2. 地政学リスクとは?わかりやすく解説

ビジネスに直結する地政学リスクを正しく捉えるためには、その根底にある「地政学」という考え方を理解することが出発点となります。ここでは、歴史的背景から現代におけるリスクの多様化までを整理し、企業担当者が押さえておくべき基本的な枠組みを解説します。
(1)地政学とは?定義をわかりやすく解説
地政学とは、地理的条件が国家の戦略や国際関係にどのような影響を与えるかを解き明かす学問です。19世紀末にヨーロッパで発展し、当初は領土の拡張や資源確保といった「生存戦略」に重点が置かれていました。大陸国家と海洋国家の対立構造、シーパワーやランドパワーといった概念は、当時の国家戦略を理解するうえで不可欠な理論でした。
しかし、現代の地政学は単なる軍事や領土の問題にとどまりません。グローバル経済の相互依存、エネルギーや食料の供給網、情報技術やサイバー空間の安全保障といった要素が複雑に絡み合い、ビジネス環境にも直接的な影響を与えています。地政学リスクはもはや遠い国の出来事ではなく、サプライチェーンの寸断や市場変動を通じて企業活動に直結する現実の課題となっているのです。
(2)2025年の日本における地政学リスク一覧
地政学リスクは、政治・経済・社会・環境といった複数の要素に起因し、単独でも、また複合的に企業活動へ大きな影響を及ぼします。以下にそれぞれの特徴を整理しました。
| リスクの種類 | 具体例 | 企業活動への影響 |
| 政治的リスク | 政権交代、外交摩擦、武力衝突 | 政策変更や紛争により事業環境が急変 |
| 経済的リスク | 資源価格の急騰、為替の急変動、制裁措置 | 調達コストや収益に直結 |
| 社会的リスク | テロ、大規模デモ、移民問題 | サプライチェーンや現地拠点の稼働を妨害 |
| 環境的リスク | 異常気象、自然災害、インフラ被害 | 物流の停滞や設備損壊に直結 |
これらのリスクは互いに独立して存在するのではなく、複雑に絡み合いながら「複合リスク」として顕在化するケースが多いのが実情です。企業担当者は、分野ごとに個別で管理するのではなく、全体を包括的に把握したうえで、自社への影響度を事前に評価しておくことが不可欠です。
(3)地政学リスクと地政学的リスクの違い
「地政学リスク」と「地政学的リスク」は似たように使われますが、専門的にはニュアンスが異なります。
地政学リスク
・地理的条件や国際関係がもたらす広義の潜在的影響
・地形・資源分布・航路など地政学的要素そのものが内包する不確実性
地政学的リスク
・地政学的要因が現実化した具体的事象
・軍事衝突・経済制裁・通商摩擦など顕在化した危機
つまり「地政学リスク」はより抽象的で構造的なリスクの枠組みを指し、「地政学的リスク」はその枠組みが具体的に顕在化した現象や事象を指す傾向があります。実務的に両者は混用されることも多いですが、企業のリスクマネジメントにおいては、抽象的リスク(構造的要因)と具体的リスク(顕在化した事象)を区別することが有効です。
(4)2025年に懸念される地政学ランキング
2025年は「米国一強時代の終焉」「安保ファーストの経済運営」「ポピュリズムの常態化」という3つの大きなトレンドを背景に、複数の地政学リスクが顕在化する可能性があります。以下の表は、その10大リスクを整理したものです。
| 順位 | リスクの種類 | リスク概要 |
| 1位 | トランプ2.0 | トランプ政権復帰による外交政策の不透明化。米国政治の機能不全が進み、同盟関係や国際秩序が揺らぐリスク。 |
| 2位 | ウクライナ戦禍の年 | 戦闘の長期化、停戦交渉の停滞により、NATOや西側諸国の分断を招き、安全保障の不安定化をもたらす。 |
| 3位 | 中東情勢の混迷 | ガザ紛争の長期化、イランの核開発問題などで地域不安が拡大し、世界的なエネルギー市場に影響。 |
| 4位 | 東アジア情勢の混乱 | 台湾有事リスクや米中関係の悪化、日本や韓国の防衛費増大などが地域の緊張を高める。 |
| 5位 | 貿易戦争の再発 | 米中の経済摩擦の再燃。半導体や重要鉱物の供給網を巡る対立が激化し、世界経済に打撃。 |
| 6位 | 中国経済のリスク化 | 不動産市場の不安定化、人口減少、外資流出により、中国経済が減速。世界の成長エンジン低下へ。 |
| 7位 | グローバルサウスの取り込み合戦 | 西側と中国・ロシアの間で発展途上国の取り込み競争が激化。外交・経済支援を巡る対立が表面化。 |
| 8位 | サイバー・認知戦の激化 | 国家主導のサイバー攻撃やSNSを通じた情報操作が拡大し、企業や社会基盤への脅威が増大。 |
| 9位 | グリーンバックラッシュの拡大 | 脱炭素政策への反発が世界的に広がり、環境政策と経済成長の両立が困難化。 |
| 10位 | DEI運動の普及 | ジェンダー・人種・多様性に関する社会運動が国内政治の分断要因となり、企業経営にも影響。 |
3. 地政学リスクが企業経営に与える影響

地政学リスクは抽象的な概念にとどまらず、実際の企業活動に直接的な打撃を与える要因となっています。国際情勢の不安定化は、サプライチェーンや資金調達、規制対応など多方面に波及し、企業経営の根幹を揺るがすリスクへと発展しかねません。ここでは、地政学リスクが企業経営に与える影響と代表的な事例についても解説します。
(1)サプライチェーン寸断とコスト上昇
たとえば、日本企業が台湾や韓国、中国など海外拠点に依存していた半導体製造部材の入手が、輸送遅延や国際情勢の変化によって急に不安定化した事例があります。
このような寸断が現実化すると、企業はまず代替の供給先を探し、あるいは十分な在庫を前倒しで確保するしかなく、結果としてコストの跳ね上がりを避けられません。
実際に、台湾のTSMC(台湾積体電路製造)が熊本第2工場を新設した事例があります。
これは台湾有事や米中対立、パンデミックに備えた供給網の確保が背景にあります。
先端半導体の生産拠点確保としても有効であり、攻守一体の企業事例として注目を集めています。
参考:
https://www.mof.go.jp/pri/research/conference/fy2024/naigai202501_5.pdf
(2)マーケット変動と需要リスク
地政学リスクは、為替レートの急激な変動は輸出入価格に直結し、特に原材料を海外に依存する企業にとっては収益構造を大きく変えるリスクとなります。
特定国や地域で景気後退が進めば需要が急減し、販売計画の修正や在庫の滞留につながり、株式市場や為替市場のボラティリティを高めた結果、企業の資金調達コストが上昇する恐れもあります。
たとえば、アメリカのファストフードチェーンのマクドナルドは、ロシアによるウクライナ侵攻によって、ロシア市場から撤退し、日本円でおよそ1500億円から1800億円の損失が見込まれています。
このような紛争による地政学リスクは一国や地域にとどまらず、世界的な需要の変動を通じて企業の収益基盤そのものを揺るがす要因となり得ます。
(3)法規制・通商政策の急変リスク
国家間の対立や貿易摩擦は、突然の関税引き上げや輸出入規制強化として表れ、企業活動に直撃します。
たとえば、2025年における自動車関税の場合、従来の6倍に最終決定し、自動車業界トップや経済界から不安の声が挙がっています。
こうした急変は下請けや物流業者にも波及するため、複数ルートでの調達体制や事前のリスクシミュレーションが不可欠です。
4 まとめ
地政学リスクは、国際政治や軍事の専門領域にとどまらず、企業経営や投資判断に直結する実務的な課題です。この記事で紹介した書籍はいずれも、基礎から応用、そして具体的なリスクシナリオまで多角的な学びを提供してくれる内容となっています。激変する世界において、企業担当者が的確な意思決定を行うには、こうした知識を継続的にアップデートし、戦略に活かしていく姿勢が欠かせません。ぜひ本記事をきっかけに、地政学リスクを正しく理解し、自社の競争力強化へとつなげてください。