管理職の素質がある人の特徴|昇格で失敗しない人選、人材不足の対処法も解説

管理職の人選において重視すべき事項は、優秀なプレイヤー(作業者、あるいは一般職)が必ずしも管理職として有能とは限らないことです。経営者とプレイヤーに適不適があるように、管理者においても一定の適不適があるためです。
この記事では、管理職に適した素質や特徴を解説します。管理職における人選で失敗しないためにお役立てください。
管理職と一般職の違いは「求められる役割」と「視座の高さ」

管理職と一般職はなる職位の差ではなく、その役割と視座の高さに大きな違いがあります。両者の役割をみると必要な視点が異なることが明らかです。
管理職と一般職の主な役割
- ・一般職:自分の業務範囲内で目の前のタスクを確実にこなす
- ・管理職:組織全体を俯瞰し、チームやプロジェクト全体を牽引していく
ここでは、上記のような管理職と一般職の違いを責任範囲や判断といったより細分化した項目から解説します。
責任範囲
以下の表は、一般的な企業における管理職と一般職における責任の違いです。
| 管理職 | 一般職 | |
| 責任範囲 | チームや部署全体の成果 | 自身が担当する業務 |
| 責任の重さ | 業績責任や人材育成 →失敗が企業全体に影響を及ぼす場合も | 個人レベルの業務達成 |
管理職では責任範囲が広がることで、一般職よりもリスク管理が求められる場面が増え、同時にその重さを実感することが多くなります。
判断力
管理職の判断力が弱いと、業務の停滞やトラブルの長期化を招き、チーム全体に悪影響を及ぼします。よって、裁量の有無は管理職と一般職におけるわかりやすい違いともいえるでしょう。
| 管理職 | 一般職 | |
| 意思決定力 | 重要な意思決定が増える | 裁量がない場合が多い |
| 判断力 | 適切な対応策を自分で考えることが多い | 業務の正確性や効率性を局所的に思考する |
建設業界におけるプロジェクト管理の現場では状況が刻々と変化するため、管理職には特に的確な意思決定が求められます。
チームをまとめるコミュニケーション力
管理職はリーダーシップを発揮しながら、チーム全体のモチベーションを維持し、スムーズな業務遂行を心がける必要があります。
管理職に求められるコミュニケーション力
- ・伝達力
- ・傾聴力
- ・フィードバック力
- ・調整力
- ・共感力
上記をすべて兼ね備える人物を選定するのは困難な場合があるため、総合的な視点での選出が重要です。
長期的ビジョンと戦略性
管理職は戦略性をもって業務にあたることが求められます。
管理職に求められる戦略性とは
- ・明確な目標設定
- ・戦略の立案と実行計画
- ・PDCAサイクルの徹底
- ・社員への共有とモチベーション向上
一般職も自社における長期的なビジョンを理解すべきですが、管理職の場合はそれが職務をまっとうするうえで前提条件となります。
管理職の素質がある人物の特徴を対人スキル・判断力・安定感に分けて解説

管理職の素質は、その人物の特徴に現れる場合があるため、人選における目安にすることができます。
ここでは、対人スキル・判断力・安定感の3つの観点から、管理職の素質がある人物の特徴を解説します。
管理職に必要な対人スキルに関する特徴

管理職には、全体的なコミュニケーション能力をもとにした信頼関係の構築が求められます。以下では、対人スキルを備えた管理職の特徴を解説します。
普段から不適切な発言をしない
清廉潔白な人物でなくても、人を不快にさせる余計な一言を無意識に言わない人物が管理職に適任です。発言が適切かどうかはその場にいる人物の判断であっても、無自覚に余計な一言を繰り返してしまう場合、指摘では治らない可能性が高いためです。
不適切な発言をしないかどうかは、以下のような日常的にありがちな余計な一言を言うかどうかで目安にできます。
| 会議で人格否定にあたる感想を言う | 「〇〇さんにはわからないだろうけど…」など |
| デリケートなプライベートに触れる | 「結婚しないんですか?」など |
| 困っている場面で突き放す発言 | 「自分で考えて」「いや、でも実際はこうですよ」など |
管理職の素質がある人は、上記のような自分勝手な発言はしない傾向にあります。
人の話を遮ることなく最後まで聞ける
気質的に積極的なコミュニケーションを図れる人物でなくても、最後まで人の話を聞ける人物であれば多くの人から好印象を抱かれやすくなります。
まずは最後まで話を聞いてから意見できる人物であれば、コミュニケーション面に課題があるとしても改善を目指すことができるでしょう。
誰にでも平等に接することができる
公平な視点を備えた人物なら、部下が安心して業務に集中できます。
どの従業員も経営者の前ではなるべく良い自分を演じるものの、以下のような確認で、その人物の公平性を判断しやすくなります。
| 基準 | 確認方法 | |
| 評価・フィードバックの一貫性 | 特定の人だけが根拠なく高評価になっていないか | ・定期的に評価プロセスを見直す・他メンバーからの意見を収集する |
| 部下からの信頼度 | 部下が「公平だ」と感じているかどうか | ・個別面談で直接管理職社員の印象を聞く |
| チームパフォーマンスの安定性 | 管理職の評価がチームのパフォーマンスにどのように影響しているか | ・業績データの分析(特定メンバーの成果偏りをチェック) |
他者の成果を素直に認めて称賛できる
他者の成果を素直に認めて称賛できる管理職は、信頼関係を築き、チーム力を引き出すリーダーシップを持っています。
| 特徴 | 発言例 |
| 部下や同僚への配慮がある | 「何か困っていることない?」「サポートが必要なら遠慮なく言ってね」 |
| 自主性を引き出すコミュニケーションができる | 「それ、面白そうだね。もう少し聞かせてくれる?」「失敗は誰でもあるよ。次に活かすためにはどうする?」 |
| チームの成果を重視できる | 「みんなのおかげで成功できたね!」「あの準備のおかげでスムーズに進んだよ。」 |
上記のような特徴を備えた人物は、管理職に適切な称賛力を備える可能性があります。
管理職に求められる判断力に関する特徴
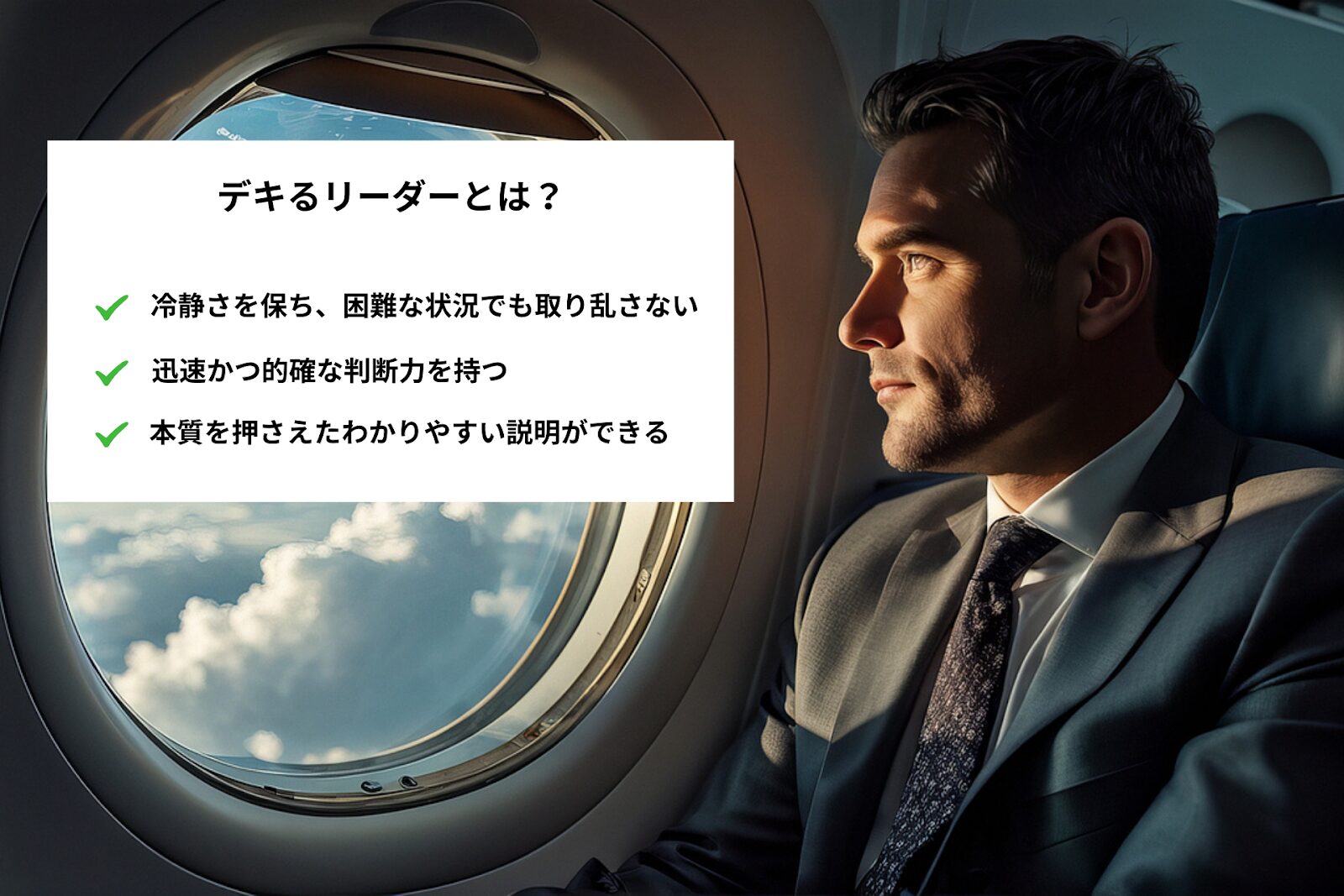
管理職は周りの意見を尊重しつつ、自らの判断を適切に下す必要があります。
ここでは、管理職に求められる判断力に関する特徴を解説します。
困難な状況でも冷静
たとえば、チームが混乱しているときこそリーダーである管理職が落ち着いていることで、周囲の不安を和らげ、的確な対応が可能となります。
そのような対応が期待できる人物には、以下のような特徴があります。
- ・突発的なトラブルでも声を荒げない
- ・他人の失敗やミスに対して感情的な反応をしない
- ・事実と憶測を区別できる
判断が難しい場合には、周囲の同僚や部下から困難な状況での対応について情報収集することも有効です。
どんなことにも決断が速い
決断の速さは、日常業務やシミュレーションを通じて、その判断力を以下のように観察・評価するのが効果的です。
| ポイント | 発言例 |
| 仮説を立てて即座に行動に移す | 「このケースならAかBの選択肢がありますが、リスクの少ないAで進めましょう」 |
| リスクを最小限にする工夫があるか | 「万が一の時はB案に切り替える準備をしておきましょう」「まず小規模でテストし、結果が良ければ本格導入します」 |
| 経験とデータに基づいた即決力があるか | 「以前似たケースで成功した方法を使います」「データを見る限り、この方法が最も効果的です」 |
決断の速さと正確性をあわせもつ管理職を選出することで、全体の生産性を向上させ、自社の利益の最大化を目指すことができます。
本質を押さえた説明ができる
本質を押さえた説明ができる管理職は、部下や取引先に対してわかりやすく要点を伝えられるため、コミュニケーションや業務指示がスムーズになります。
本質的な説明は全ビジネスマンに求められるものの、中小企業では少数精鋭で迅速な意思疎通を図ることが求められるため、シンプルで的確な説明力が特に重要です。
説明力を備える人には、以下の特徴があります。
| 特徴 | 発言例 |
| 要点をシンプルにまとめられる | 「結論としては、〇〇を優先するべきです」 |
| 相手の立場や知識レベルを考慮できる | 「簡単に言うと、〇〇ということです」「ここまででご不明点はありますか?」 |
| 具体例をうまく使える | 「イメージしやすく言うと、△△のような感じです」「これは車のメンテナンスと似ています。日々の点検が重要です」 |
| 質問や反論にも適切に対応できる | 「その点については、〇〇を考慮して決めました」「ご意見ありがとうございます。しかし、こういった背景があるため、この方向が適切です」 |
日常の報告や打ち合わせの中で、無駄がなく、わかりやすい説明をしているかを観察すると、適性が判断しやすくなります。
管理職に求められる安定感と人間性に関する特徴
安定感と人間性はビジネスマンであればある程度求められる要素です。
ここでは、管理職の健全な持続性を評価したい場合に基準となるポイントとして紹介します。
自己管理能力が高く行動に計画性がある
スケジュール管理が適切に行える管理職は、仕事上の納期を遵守できます。
締め切りに余裕をもって業務に取り組み、スケジュール帳やタスク管理ツールなどの忘却を未然に防ぐ仕組みを充実させています。
家族仲などの人間関係が安定している
雑談などで家族の話題が挙がる場合には、家族仲が良好で適切なサポートを得られている可能性が高いです。
「週末は家族サービスをしています」「趣味の集まりでリフレッシュしています」など、自然な発言で確認できる場合があります。
程よく真面目な気質である
真面目さは業務を誠実にこなすうえで大切な要素ですが、過度に堅苦しい態度や完璧主義が行き過ぎると、部下や同僚とのコミュニケーションが難しくなる恐れがあります。
真面目具合のバランスは、周囲の評価やコミュニケーションを目安に判断できます。
同僚と自然にコミュニケーションができている場合には、程よく真面目な気質を持ち合わせる人物である可能性が高いです。
管理職に向いていない人の特徴とは?適材適所の人選を解説

適材適所で人選を行うためには、管理職に向いていない特徴もあわせて理解しておくことが大切です。なお、内容や度合いによっては経験でまかなえる場合ももちろんあるため、あくまでも参考程度にお役立てください。
管理職に向いていない特徴を把握し、慎重に人選を行いましょう。
部下の業務を抱え込みすぎてしまう
管理職自身の業務量が増えすぎてしまうと、結果的にリーダーシップや意思決定に支障をきたし、持続的ではなくなる場合があります。
このような人物の場合、以下のような考えが根底にある場合が多いです。
業務を抱え込みすぎてしまう人の特徴
- ・ミスがあってはいけないから、自分で確認しておこう
- ・自分でやった方が早いし確実
- ・自分でやらないと示しがつかない
部下の業務を抱え込みすぎる人物は、責任感や完璧主義、信頼不足が原因であることが多いです。
気分屋で周囲に悪影響を及ぼす
気分屋な性格を持つ人が管理職に就くと、部下やチーム全体に悪影響を及ぼします。このような人物は客観的にもわかりやすく、以下のような特徴があります。
周囲に悪影響を及ぼす人の特徴
- ・状況や人によって態度がコロコロ変わる
- ・機嫌が悪いと急に怒鳴りだす
- ・感情の浮き沈みが激しい
プレイヤーとして優秀すぎてマネジメントが疎かになる
プレイヤーとして優秀すぎる人物が管理職になった場合、自らが手を動かしたほうが効率的と考えてしまい、部下に業務を任せることができない状況が生まれます。
程度の差はあるものの、他者育成意識が極端に低い場合には部下を持つことそのものが不向きなケースもあるでしょう。
プレイヤーとして優秀でもマネジメントが向いてない人の特徴
- ・スキルや経験に自信がありすぎて、自分でやってしまう
- ・個人で成果を出すことが最優先になっている
- ・チーム全体の協力体制を整える意識が薄い
発言が一貫せず指示内容がぶれることが多い
指示がぶれる原因として考えられるのは、管理職自身が方針や方策を十分に理解できていないことです。以下のようなブレやすい性質がある場合に該当します。
指示内容がぶれることが多い人の特徴
- ・状況に流されやすく優柔不断
- ・深く考えずに場当たり的な発言をする
- ・自信がなく周囲の反応を気にしすぎる
柔軟な対応を通り越して一貫性がなさすぎる人物が管理職になった場合、現場の混乱しやすくなるため注意しましょう。
自分のミスを認めず責任を押し付けがち
以下のように管理職がミスを認めずに部下や他者へ責任を押し付けがちだと、信頼関係が崩れ、チーム全体のモチベーションが低下する原因となります。
ミスを認めず責任を押し付けがちな人の特徴
- ・言い訳や正当化が多い
- ・失敗時は他人の責任にする
- ・自己正当化を繰り返す
ミスを隠すために嘘をつくことが重なると、企業全体の信用にも重大な悪影響が及びます。
自分のやり方に固執して新しい方法を受け入れない
管理職の仕事への自信が過剰になると、過去のやり方に固執しすぎてしまい、新しい方法や改善策を受け入れにくくなるリスクがあります。
自分のやり方に固執する人物の特徴として、以下のような成功体験への依存などがあります。
自分のやり方に固執して新しい方法を受け入れない人の特徴
- ・過去の成功体験に依存している
- ・自分が正しいと思い込んでいる
- ・学ぶ意欲がなく自己成長を怠っている
その結果、若手社員や部下が提案する新しい手法やアイデアを否定的に見てしまうことが増えます。
コミュニケーションが上司中心で部下との連携が不足している
コミュニケーションが上司中心になりすぎると、部下との連携が不足しチーム全体のパフォーマンスに深刻な悪影響を及ぼします。そのような人物の場合、以下のような問題を確認できます。
部下との連携が不足している人の特徴
- ・部下への情報共有が不足している
- ・上司の評価を気にしすぎて部下のフォローが疎か
- ・指示や命令が上司視点ばかりで部下の意見を無視する
個人単位の問題では留まらないため、深刻化すると現場で働くメンバーが状況を正確に把握できず業務が混乱しやすくなります。
管理職に昇格させたい人材が不足している場合の対処法

企業の現場では「管理職に適した人材が不足している」「リーダーシップを発揮できる社員が見当たらない」といった課題に直面することが多いです。管理職候補者が不足している場合にどのような対策を講じればよいのか、その具体的な対処法について詳しく解説します。
なお、以下の記事では管理職の退職後に後任がいない場合の緊急性が高い状況下での打開策も解説しています。
社員教育でリーダーシップを育てる
リーダーシップを備えた社員が増えることで、企業全体が自主性と創造性にあふれ、活気ある職場環境が実現します。
| 具体例 | |
| ロールプレイング | ディスカッション形式の研修を活用する |
| ケーススタディ | 問題発見から解決策の立案までを体験できる研修を行う |
| チームビルディング | メンバーとのコミュニケーションが必須になる研修を行う |
これらの手法を通じて、現場で必要とされるリーダーシップスキルを実践的に学べる環境を整えれば、社員の自主性や指導力の向上が期待できます。
結果として組織全体のパフォーマンスが底上げされ、活気ある職場環境が実現できるでしょう。
外部から優秀な人材を採用する
外部から優秀な人材を採用するには、求める人材像を明確にし、転職サイトなどの媒体で情報公開することも有効です。転職サイトなどへの掲載は比較的すぐに始められ、不特定多数の人への発信に有効ですが、掲載には費用がかかることが一般的です。
そのため、採用までのタイミングや目的によっては向かないケースがあります。
採用ブランディングにホームページを活用する
採用ブランディングに専用ホームページを作成することで、長期的な自由度を備えた情報発信が可能となります。なお、当サイトでは企業様ごとの採用ブランディングに特化したホームページ作成のご依頼を承っており、コチラからお問い合わせいただけます。
採用ブランディングを意識したホームページを整えることで、優秀な人材を惹きつけ、企業の成長を後押しする力となります。
まとめ
適切な管理職を育成・配置するためには、対人スキルや意思決定力、長期的ビジョンを持つかどうかをしっかりと見極めることが重要です。また、管理職としてふさわしい素質を持つ社員が不足している場合には、人材育成や採用ブランディングを戦略的に行うことも有効です。
もし社内に管理職の人材が不足している場合には、ホームページによる情報発信が有効です。当サイトでも承っていますので、企業のホームページ制作に関して、不安や疑問があればコチラからお気軽にご相談ください。